松葉杖でもバス・電車に乗るのは結構怖い ― 2007年04月05日 19時12分22秒
女性専用車両:利用できるのに…視覚障害の男性、困惑
(by 毎日新聞)
全盲の障害者の方が、女性専用車両に意図せず乗ってしまった時の顛末です。
女性専用車両についての扱いは鉄道各社によってまちまちだそうですが、基本的には「女性や子供、障害者」など、弱い立場の方々を守るためにあるものだそうな。女性が弱いなんていうのもまた人によってはセクハラに感じるんでしょうけど。
ただし「原則」であり、場合によっては男性が乗車する事もある、とのこと。夫婦で別の車両なんてのも変な話ではありますからね。
これはあくまで鉄道会社の取り決めで、これを破ったからと言って法的な措置が直ちに取られる・・・という事は無いと思います。
(もっともあらぬ疑いを掛けられる確率は高くなりそうですが)
この女性専用車両がどこに設定されるかはまちまちのようですが、車両の端っこかど真ん中か、二択。大体半々の分布です。
参照先のケースは東武野田線、端っこパターンです。
またトラブルに巻き込まれた男性は、七里駅から大宮駅までの利用だそうですが、この七里駅、 上下ホームが中央付近の階段で結ばれた構造です。
この構造だと、恐らく人はホーム中央に集中すると思います(七里駅の乗降者数がどれほどなのかにもよりますが)。大宮方面ならば先頭方向です。
障害を持っている方は、人を避けようとしてホームの端っこに向かい(或いはいつもの定位置か)、そこでたまたま女性専用車両に乗ってしまったんじゃないかと思います。
障害者の利用も想定しているということですが、「女性」と「障害者」の要求事項は違います。
女性が恐れているのは、これまた勝手な予想ですが、「痴漢犯罪者」でしょう。
これは私の想像も及ばないぐらいの恐怖であるのだろうと思います。つまり「犯罪者の隔離」こそが求むる事。
対して障害者の場合は、座席の確保など機能的な要求の方が大きいでしょう。
つまり。「女性専用」と「障害者用」は切り離して考えるべきでしょう。
具体的には優先席専用車両を作ってしまう。草の根からの意見の引用です。
女性専用車両は別にどこだっていいのですが、障害者は出来るだけ人との接触が少ない方が、不測の事態が起こらない。そういう場所に確保すべきでしょう。
もっとも障害者の鉄道利用がどれだけあるか、という話になりますので、どこの車両に乗っても、気遣ってあげる事で全て解決する事です。
以下強調部分の各論です。
1.女性専用車両に乗った女性の心理
あくまで個人的な見解ですが。
いくら女性専用車両とはいえ。
間違って乗った障害者の方に罵声を浴びせるのがまともな神経だとは思えません。
「専用」という言葉で自分の位置を見失ってしまっているんじゃないですかね。
「女性専用車両に乗った女性」は絶対権力者、ではないです。善良な一市民、のはずです。
「守られている」と感じる事で、安心感を持つ事は大いに結構。しかし別に「優遇されている」わけではないと言う事を、よーく確認して欲しいです。
一般常識を見失わせるほどの限定空間じゃないって事です。
2.鉄道会社及び我々の認識不足
女性専用と謳ってはいるものの、実際には子供とか障害者の方などの利用も想定している。
なのに間違った認識でいるのはなぜか。名前が悪いに決まっているだろっ。
なんでよりによって「女性専用車両」なんて名前にしてしまったか。これでは100%「女性しか乗っちゃいけない」と思う。この名前からその奥の想定範囲を想像するのは無茶な話。
ぶっちゃけ、もう「女性専用」って名前はやめにしませんか?ロクなことないですよ。
3.参照先記事のケースでの女性の対応
えー、はっきり言って、赤点の対応です。
記事では「注意された」という書き方になってはいますが、その女性がどういう考えで言ったのかは、文面からだけではわかりません。
しかし出た言葉だけ見ると、利口な対応ではありません。
例えばの話ですが。
「ここは女性専用車両ですよ」の後に、
「もし一般車両に移動されるなら手をお貸しいたしますが、いかがなさいますか?」
などと付け加えていれば、たぶんこんな記事になりはしなかったでしょう。
対応が不味かったから新聞なんぞに書かれちまった。
難しいもので、自分の心の中と言葉は比例しませんから、行き違いが起きます。
これはもうケーススタディでも何でもいいですから、相手に優しい言葉遣いを選択してください。
本心と違う解釈でバッシングされるのは不本意でしょうから。(本当はどう思ったか分からんけど)
4.障害者の鉄道利用に際し
この一件ですっかり打ちのめされてしまった障害者の方は、ヘルパーさんに依頼する事に。
結構なショックだったと思います。
女性専用車両に乗っても規約上は問題ないのに、ヘルパーさんを雇ってまで一般車両に確実に乗るようにした、ということは、余程女性の対応がショックだったのか女性に余計な心配を掛けない為の心配りか。
こうなる前に鉄道各社が出来た対応はあったと思いますが、ヘルパーさんにお願いするのは賢い選択でしょう。
やはりハンディキャップがあると、身体機能的には不利です。それを補ってくれるパートナーは、必要になります。
本当は、ラッシュ時に乗るのはハイリスクだから避けたほうが良いのですが・・・
そうも言ってられないと言われればそれまでですが、病院の時間をずらしてもらうとか、或いは他の交通を利用するとか、とにかく安全性を第一に考えてベストな選択をしてもらいたいですね。
ネットなんかでは、このニュースに対するコメントとして「女性へのバッシング」が目立っていますね。
まあこれは今に始まった事ではありませんが・・・
バッシングはどうでもいいのですが、これで障害者の方への気遣いとかの有り方を考えてくれるようになれば・・・無理かなぁ。
そもそも女性専用車両が出来た背景には痴漢犯罪があるのだから、まずはその痴漢犯罪を撲滅する事が先決だと言う人もいるでしょうね・・・ただ幾ばくかの痴漢のケースは勘違いとか自作自演も含まれているとかいないとか。
一概に撲滅といっても終着点が見えない以上は100%は無理ですね。
そのうち電車が半々、男性女性で分かれるようになるんじゃないかと思っちゃいます。行き過ぎでしょうが。
女性としては、恐らく「犯罪者(≒男性)の隔離」だと思うので、いっそオフピーク通勤にしちゃった方がよいのではないでしょか?
この辺、女性自らの働きかけという事で、あの怪獣にひと暴れしてもらった方が良いかも?w
(by 毎日新聞)
全盲の障害者の方が、女性専用車両に意図せず乗ってしまった時の顛末です。
4つ強調部分を設けました。個人的に気になったからですが・・・首都圏を中心に、女性専用車両を導入する鉄道会社が増えている。朝のラッシュアワーに、女性を痴漢から守るためだ。しかし、女性専用と分からないまま車両に足を踏み入れ、冷たい言葉を投げつけられる視覚障害の男性たちもいる。この車両、障害のある男性も利用できることになっているが、一般には知られていない。身が凍り付くような経験をした障害者らは「交通弱者も利用できることをもっと知らせてほしい」と訴えている。さいたま市見沼区に住む全盲の男性(41)は毎週2回、持病の療養施設に通うため東武野田線の七里-大宮間を利用する。同線は05年6月以降、平日の早朝から午前9時まで、6両編成のうち最後尾1両を女性専用車両とした。1年半ほど前、何気なく電車に乗ったところ、「ここは女性しか乗れませんよ」と女性客に注意された。冷たい空気が車両に広がった。恥ずかしくて逃げ出したくなったが、満員で身動きも取れない。揺れる電車の中でじっと耐えた。この時以来、男性はヘルパーを駅まで同伴して確実に一般車両に乗ることにしている。(強調は筆者)
女性専用車両についての扱いは鉄道各社によってまちまちだそうですが、基本的には「女性や子供、障害者」など、弱い立場の方々を守るためにあるものだそうな。女性が弱いなんていうのもまた人によってはセクハラに感じるんでしょうけど。
ただし「原則」であり、場合によっては男性が乗車する事もある、とのこと。夫婦で別の車両なんてのも変な話ではありますからね。
これはあくまで鉄道会社の取り決めで、これを破ったからと言って法的な措置が直ちに取られる・・・という事は無いと思います。
(もっともあらぬ疑いを掛けられる確率は高くなりそうですが)
この女性専用車両がどこに設定されるかはまちまちのようですが、車両の端っこかど真ん中か、二択。大体半々の分布です。
参照先のケースは東武野田線、端っこパターンです。
またトラブルに巻き込まれた男性は、七里駅から大宮駅までの利用だそうですが、この七里駅、 上下ホームが中央付近の階段で結ばれた構造です。
この構造だと、恐らく人はホーム中央に集中すると思います(七里駅の乗降者数がどれほどなのかにもよりますが)。大宮方面ならば先頭方向です。
障害を持っている方は、人を避けようとしてホームの端っこに向かい(或いはいつもの定位置か)、そこでたまたま女性専用車両に乗ってしまったんじゃないかと思います。
障害者の利用も想定しているということですが、「女性」と「障害者」の要求事項は違います。
女性が恐れているのは、これまた勝手な予想ですが、「痴漢犯罪者」でしょう。
これは私の想像も及ばないぐらいの恐怖であるのだろうと思います。つまり「犯罪者の隔離」こそが求むる事。
対して障害者の場合は、座席の確保など機能的な要求の方が大きいでしょう。
つまり。「女性専用」と「障害者用」は切り離して考えるべきでしょう。
具体的には優先席専用車両を作ってしまう。草の根からの意見の引用です。
女性専用車両は別にどこだっていいのですが、障害者は出来るだけ人との接触が少ない方が、不測の事態が起こらない。そういう場所に確保すべきでしょう。
もっとも障害者の鉄道利用がどれだけあるか、という話になりますので、どこの車両に乗っても、気遣ってあげる事で全て解決する事です。
以下強調部分の各論です。
1.女性専用車両に乗った女性の心理
あくまで個人的な見解ですが。
いくら女性専用車両とはいえ。
間違って乗った障害者の方に罵声を浴びせるのがまともな神経だとは思えません。
「専用」という言葉で自分の位置を見失ってしまっているんじゃないですかね。
「女性専用車両に乗った女性」は絶対権力者、ではないです。善良な一市民、のはずです。
「守られている」と感じる事で、安心感を持つ事は大いに結構。しかし別に「優遇されている」わけではないと言う事を、よーく確認して欲しいです。
一般常識を見失わせるほどの限定空間じゃないって事です。
2.鉄道会社及び我々の認識不足
女性専用と謳ってはいるものの、実際には子供とか障害者の方などの利用も想定している。
なのに間違った認識でいるのはなぜか。名前が悪いに決まっているだろっ。
なんでよりによって「女性専用車両」なんて名前にしてしまったか。これでは100%「女性しか乗っちゃいけない」と思う。この名前からその奥の想定範囲を想像するのは無茶な話。
ぶっちゃけ、もう「女性専用」って名前はやめにしませんか?ロクなことないですよ。
3.参照先記事のケースでの女性の対応
えー、はっきり言って、赤点の対応です。
記事では「注意された」という書き方になってはいますが、その女性がどういう考えで言ったのかは、文面からだけではわかりません。
しかし出た言葉だけ見ると、利口な対応ではありません。
例えばの話ですが。
「ここは女性専用車両ですよ」の後に、
「もし一般車両に移動されるなら手をお貸しいたしますが、いかがなさいますか?」
などと付け加えていれば、たぶんこんな記事になりはしなかったでしょう。
対応が不味かったから新聞なんぞに書かれちまった。
難しいもので、自分の心の中と言葉は比例しませんから、行き違いが起きます。
これはもうケーススタディでも何でもいいですから、相手に優しい言葉遣いを選択してください。
本心と違う解釈でバッシングされるのは不本意でしょうから。(本当はどう思ったか分からんけど)
4.障害者の鉄道利用に際し
この一件ですっかり打ちのめされてしまった障害者の方は、ヘルパーさんに依頼する事に。
結構なショックだったと思います。
女性専用車両に乗っても規約上は問題ないのに、ヘルパーさんを雇ってまで一般車両に確実に乗るようにした、ということは、余程女性の対応がショックだったのか女性に余計な心配を掛けない為の心配りか。
こうなる前に鉄道各社が出来た対応はあったと思いますが、ヘルパーさんにお願いするのは賢い選択でしょう。
やはりハンディキャップがあると、身体機能的には不利です。それを補ってくれるパートナーは、必要になります。
本当は、ラッシュ時に乗るのはハイリスクだから避けたほうが良いのですが・・・
そうも言ってられないと言われればそれまでですが、病院の時間をずらしてもらうとか、或いは他の交通を利用するとか、とにかく安全性を第一に考えてベストな選択をしてもらいたいですね。
ネットなんかでは、このニュースに対するコメントとして「女性へのバッシング」が目立っていますね。
まあこれは今に始まった事ではありませんが・・・
バッシングはどうでもいいのですが、これで障害者の方への気遣いとかの有り方を考えてくれるようになれば・・・無理かなぁ。
そもそも女性専用車両が出来た背景には痴漢犯罪があるのだから、まずはその痴漢犯罪を撲滅する事が先決だと言う人もいるでしょうね・・・ただ幾ばくかの痴漢のケースは勘違いとか自作自演も含まれているとかいないとか。
一概に撲滅といっても終着点が見えない以上は100%は無理ですね。
そのうち電車が半々、男性女性で分かれるようになるんじゃないかと思っちゃいます。行き過ぎでしょうが。
女性としては、恐らく「犯罪者(≒男性)の隔離」だと思うので、いっそオフピーク通勤にしちゃった方がよいのではないでしょか?
この辺、女性自らの働きかけという事で、あの怪獣にひと暴れしてもらった方が良いかも?w
あなたの「いい音楽」は何ですか? ― 2007年04月09日 22時32分12秒
音楽について語ると言う事で、先手必勝w
シリーズ◇音楽について思うこと。( 国民宿舎はらぺこ 大浴場さま)へtb!
4番目の題目についての私なりの考え方です。
曰く。
まず最初に私の音楽に対する持論を述べますと。
個人が音楽に対して言えるのは、「好き」か「嫌い」かだけである
というものです。
音楽作品に対していろいろな人が、この曲はいい、この曲は良くない、といったように評価を下していきます。
それは千差万別なものであり、それが元で喧嘩になったり議論がヒートアップしたり、もっと悪いときには荒らし行為に発展したりします。
何故このように、同じ音楽に対してこうも評価がバラバラになってしまうのか?
その答えを出す前に、ちょっと遊んでみましょう。
下の画像を見てください。赤っぽいのとちょっとピンクっぽい2色です。
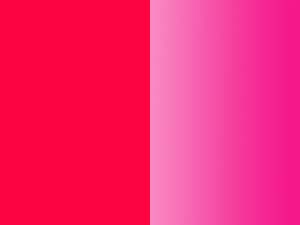
さて、どっちが赤いですか?
多分多くの人が左側の方が赤いと答えるでしょう。
じゃあ。
どっちがいい色ですか?
今度は自分の中で思い思いの考えを巡らせ、どちらかを指差すでしょう。
では。
自分の考え方が普遍的なものだと断言できますか?それを説明できますか?
誰も説明出来ません。
この2つの質問のポイント、「赤い」事と「いい」事。
両者の決定的な違い。
明確な判断基準が確立されているか否か
「赤い」事はRGBの値で決められている事です。
対して「いい」かどうかについては、万人共通の判断基準は存在しないのでどちらが「いい」かは一義的には決められず、個人個人でバラバラの結果となります。
そもそも「いい」「悪い」が何を言いたいのかも明確に説明できないですし。
それを踏まえて聞いてみます。
J.S.Bachの「トッカータとフーガ」。
オレンジレンジの「ロコローション」。
どっちが「いい曲」ですか?
結果は言うに及ばず、ですね。
このように音楽作品に対して「いい」か「悪い」かというものは、明確な判断基準が存在し得ないがゆえに結論付けられません。
もっとも、それが全てのパラメータというわけではありません。
音楽的に「正しいか」「間違ってるか」という事は判断する事が可能です。
「音楽的に正しい事=音楽理論に適合している事=楽典に従っている」と言えるでしょう。突っ込みヨロ。
となれば、音楽理論が花開いた時代の曲であれば、厳格なまでに理論通りの音楽であり、「音楽的に正しい」と言えるでしょう。
しかし「音楽的に正しい=いい」という事は言えません。
こう考えると、普段我々が「この曲はいい」「この曲は良くない」と言っているのは、個人的な判断基準によるものでしかない、という事になります。
私はその判断基準を「好き」「嫌い」という言葉で置き換えています。
さてここで改めて最初の問題提議に答えます。
・音楽作品の良し悪しの基準は聴き手個人の価値観の問題か?
その通り。
良し悪し―――「いい」か「悪い」か、というパラメータは、そもそもそれ自体が個人的な判断基準によるものである。よって結果も個人的なもの、個人的な価値観にしか成り得ない。
(ただし「音楽的に正しいか否か」のような、普遍的な判断基準が確立されれば話は別)
・音楽自体に絶対的な優劣があるわけではないか?
分からない。
そもそも音楽の優劣と言うのはどのような判断基準なのかが明確ではない。
明確ではない、万人に同意が得られていない基準では、一義的な判断は出来ない。
何故同じ音楽作品に対する評価がバラバラになってしまうのか?
みんながみんな勝手な(=個人的な)判断基準でしか評価できないから。
ってとこで。
補則すれば、明確な判断基準足りうるためには、普遍性に加えて定量性が必要かと思います。
簡単に言うと、例えば「この曲は100点満点で○○点」という判断が出来る事。さらにはいつ誰が評価しても同じ結果が出るような再現性も必要です。
評価の相関性も必要ですし・・・バリデーションでもしないといけないですかねw
逆の視点から見れば、そういった要求事項を満たせない判断基準は、所詮個人的な価値観に過ぎないと言う事です。
さらに補足すると、音楽作品に対する評価は個人の価値観から脱せないのかというと、「絶対ではない」です。
前述の通り、万人が同意しうる普遍的な判断基準が示されれば可能です。
ただ実際問題としてそんな判断基準が確立とは到底思えないのもまた然り。
前カラムで「音楽作品に対して個人が下す「いい」「悪い」という評価は、個人的な価値観に他ならない」と出ました。
これについては、反論の余地がないというよりは、実際問題としてそう考えざるを得ない、という方がいいでしょう。
少なくとも「日本の」音楽シーンは、これを否定したら成り立たないからです。
仮に、音楽作品に対する評価が万人共通の基準によって評価されているとしましょうか。
ということは、その時々に売られている作品の中で、一番「いい」ものがおのずと決まります。
CDの値段と言うのはほとんど一律です。
値段は一緒で順位付けが明確に決まっている。
となれば、その時一番いい作品だけが売れて、他のものは売れないという話になってしまいます。
でも実際はそうじゃない。
みんなが「いい」と思う作品が適度にバラけているからです。
それにもし、音楽作品に対する評価が一義的に決まるならば、音楽と言う分野は進化を止めてしまったと同じ事です。
ここで断っておきます。
音楽作品に対する評価は個人の価値観によってバラバラではありますが、音楽作品をより「いい」ものにしようとする事が無意味だとは言いません。
確かに。
価値観なんてのは個人でバラバラです。評価もまたバラバラです。聴き手としては。
しかし作り手としては、それでも自分の作品をより良くしていくものです。誰だってそうでしょう。
どうやって「良く」していくかはまたバラバラですが、それを「どうせ個人の価値観がバラバラなんだから」といって止めてしまうのは、自分の音楽の進化を止めてしまっている事です。
はっきり言って、永久に答えは出ません。
それでも、上を目指して行かないといけない。それを止めてしまったらそれ以上の進化は無いから。
極まる事の無い終着点に向かっていく事。
それに悲観して作品造りを止めてしまうのは、悲しい事だけど否定はしません。
しかし同時に、永久に究極を追い求める事が、その分野の進化のドライビングフォースであるとも言っておきましょう。
諦めたらそこで演奏終了ですよ?
もう一つ。
「音楽作品の評価は個人の価値観」ではありますが、
「評価は価値観の問題だから話し合ってもしょうがない」と考えてしまうのもまた違う。
評価と言うか価値観全般の問題ですが。
価値観なんてのは、とてもいい加減で流動的です。
環境やそのとき得た情報、果てはその日の気分でどうとでも変化します。
もちろん。
他の価値観を知ったときにも、変化します。
他の人と音楽に対する話をして、同じ作品に対する評価を聞いてみること、或いは自分の知らない作品を教えてもらう事、そうする事で自分の音楽に対する価値観は常に流動的に変化していきます。
それは、他人の価値観を知る事により、自分の価値観の幅が広がると言う事です。
そうやって「楽しみ」を増やしていく事。
これも音楽に対するあり方の一つだと思います。
クラシックこそ本物で他は邪道、と言って憚らない人も、例えばロックなんかを聴いてみると、新しい世界が開けます。
もちろん聴いても変わらない人もいますが、それもそれで価値観です。否定はしません。
大事なのは他人の価値観を無下に否定しない事。これは音楽に限らず食い物の味でもそうですが。
否定をせず、聞く事。その上で自分が思ったことを確かめればいい。
議論自体は構わないけど、自分の価値観の決め付けや押し付けを前提としたものは、敢えてそれを楽しんでいる以外は、意味が薄いでしょうね。
その人がいいと思えるならば、クラシックでもロックでも演歌でもアニソンでもラップでも、何でも本物です。
音楽作品に貴賤無し。
総括。
音楽作品に対して、個人で評価出来るのは個人の価値観内にしかならない。
個人的な価値観の問題なので、自分が気に入った音楽作品について、周りの評価がどうあれ、自分の一番大事にすべきである。
もっとも他人の下す評価を聞く事も重要であり、それを持って更なる自己の価値観の向上につなげる姿勢も大事である。
価値観の問題なので、音楽作品に対する評価が分かれたとしても、それを無意味に否定する事は望ましくない。議論によって価値観の共有から止揚へとつなげる方が望ましい。
というところです。
この他にも、コマーシャルによる誘導とかコミュニティ内の価値観の方向性の整列力なんかも関係するのですが、ややこしいのでいずれ。
ただこの段階で少しだけ触れると、音楽作品に対する考え方と言うのは、音楽外の価値観によっても多大な影響を受けてしまう、と言う事が言えます。だからこそ総合的な価値観の問題になってくるのですが・・・
ご意見お待ちしております。
シリーズ◇音楽について思うこと。( 国民宿舎はらぺこ 大浴場さま)へtb!
4番目の題目についての私なりの考え方です。
曰く。
音楽作品の良し悪しの基準は聴き手個人の価値観の問題であって、音楽自体に絶対的な優劣があるわけではないとする考え方がある。それはどこまで真実なのか?これは私の持論そのものであり、場合によっては名指しなのかも知れないと内心ヒヤヒヤw
まず最初に私の音楽に対する持論を述べますと。
個人が音楽に対して言えるのは、「好き」か「嫌い」かだけである
というものです。
音楽作品に対していろいろな人が、この曲はいい、この曲は良くない、といったように評価を下していきます。
それは千差万別なものであり、それが元で喧嘩になったり議論がヒートアップしたり、もっと悪いときには荒らし行為に発展したりします。
何故このように、同じ音楽に対してこうも評価がバラバラになってしまうのか?
その答えを出す前に、ちょっと遊んでみましょう。
下の画像を見てください。赤っぽいのとちょっとピンクっぽい2色です。
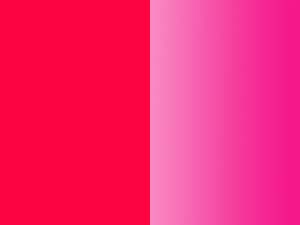
さて、どっちが赤いですか?
多分多くの人が左側の方が赤いと答えるでしょう。
じゃあ。
どっちがいい色ですか?
今度は自分の中で思い思いの考えを巡らせ、どちらかを指差すでしょう。
では。
自分の考え方が普遍的なものだと断言できますか?それを説明できますか?
誰も説明出来ません。
この2つの質問のポイント、「赤い」事と「いい」事。
両者の決定的な違い。
明確な判断基準が確立されているか否か
「赤い」事はRGBの値で決められている事です。
対して「いい」かどうかについては、万人共通の判断基準は存在しないのでどちらが「いい」かは一義的には決められず、個人個人でバラバラの結果となります。
そもそも「いい」「悪い」が何を言いたいのかも明確に説明できないですし。
それを踏まえて聞いてみます。
J.S.Bachの「トッカータとフーガ」。
オレンジレンジの「ロコローション」。
どっちが「いい曲」ですか?
結果は言うに及ばず、ですね。
このように音楽作品に対して「いい」か「悪い」かというものは、明確な判断基準が存在し得ないがゆえに結論付けられません。
もっとも、それが全てのパラメータというわけではありません。
音楽的に「正しいか」「間違ってるか」という事は判断する事が可能です。
「音楽的に正しい事=音楽理論に適合している事=楽典に従っている」と言えるでしょう。突っ込みヨロ。
となれば、音楽理論が花開いた時代の曲であれば、厳格なまでに理論通りの音楽であり、「音楽的に正しい」と言えるでしょう。
しかし「音楽的に正しい=いい」という事は言えません。
こう考えると、普段我々が「この曲はいい」「この曲は良くない」と言っているのは、個人的な判断基準によるものでしかない、という事になります。
私はその判断基準を「好き」「嫌い」という言葉で置き換えています。
さてここで改めて最初の問題提議に答えます。
・音楽作品の良し悪しの基準は聴き手個人の価値観の問題か?
その通り。
良し悪し―――「いい」か「悪い」か、というパラメータは、そもそもそれ自体が個人的な判断基準によるものである。よって結果も個人的なもの、個人的な価値観にしか成り得ない。
(ただし「音楽的に正しいか否か」のような、普遍的な判断基準が確立されれば話は別)
・音楽自体に絶対的な優劣があるわけではないか?
分からない。
そもそも音楽の優劣と言うのはどのような判断基準なのかが明確ではない。
明確ではない、万人に同意が得られていない基準では、一義的な判断は出来ない。
何故同じ音楽作品に対する評価がバラバラになってしまうのか?
みんながみんな勝手な(=個人的な)判断基準でしか評価できないから。
ってとこで。
補則すれば、明確な判断基準足りうるためには、普遍性に加えて定量性が必要かと思います。
簡単に言うと、例えば「この曲は100点満点で○○点」という判断が出来る事。さらにはいつ誰が評価しても同じ結果が出るような再現性も必要です。
評価の相関性も必要ですし・・・バリデーションでもしないといけないですかねw
逆の視点から見れば、そういった要求事項を満たせない判断基準は、所詮個人的な価値観に過ぎないと言う事です。
さらに補足すると、音楽作品に対する評価は個人の価値観から脱せないのかというと、「絶対ではない」です。
前述の通り、万人が同意しうる普遍的な判断基準が示されれば可能です。
ただ実際問題としてそんな判断基準が確立とは到底思えないのもまた然り。
前カラムで「音楽作品に対して個人が下す「いい」「悪い」という評価は、個人的な価値観に他ならない」と出ました。
これについては、反論の余地がないというよりは、実際問題としてそう考えざるを得ない、という方がいいでしょう。
少なくとも「日本の」音楽シーンは、これを否定したら成り立たないからです。
仮に、音楽作品に対する評価が万人共通の基準によって評価されているとしましょうか。
ということは、その時々に売られている作品の中で、一番「いい」ものがおのずと決まります。
CDの値段と言うのはほとんど一律です。
値段は一緒で順位付けが明確に決まっている。
となれば、その時一番いい作品だけが売れて、他のものは売れないという話になってしまいます。
でも実際はそうじゃない。
みんなが「いい」と思う作品が適度にバラけているからです。
それにもし、音楽作品に対する評価が一義的に決まるならば、音楽と言う分野は進化を止めてしまったと同じ事です。
ここで断っておきます。
音楽作品に対する評価は個人の価値観によってバラバラではありますが、音楽作品をより「いい」ものにしようとする事が無意味だとは言いません。
確かに。
価値観なんてのは個人でバラバラです。評価もまたバラバラです。聴き手としては。
しかし作り手としては、それでも自分の作品をより良くしていくものです。誰だってそうでしょう。
どうやって「良く」していくかはまたバラバラですが、それを「どうせ個人の価値観がバラバラなんだから」といって止めてしまうのは、自分の音楽の進化を止めてしまっている事です。
はっきり言って、永久に答えは出ません。
それでも、上を目指して行かないといけない。それを止めてしまったらそれ以上の進化は無いから。
極まる事の無い終着点に向かっていく事。
それに悲観して作品造りを止めてしまうのは、悲しい事だけど否定はしません。
しかし同時に、永久に究極を追い求める事が、その分野の進化のドライビングフォースであるとも言っておきましょう。
諦めたらそこで演奏終了ですよ?
もう一つ。
「音楽作品の評価は個人の価値観」ではありますが、
「評価は価値観の問題だから話し合ってもしょうがない」と考えてしまうのもまた違う。
評価と言うか価値観全般の問題ですが。
価値観なんてのは、とてもいい加減で流動的です。
環境やそのとき得た情報、果てはその日の気分でどうとでも変化します。
もちろん。
他の価値観を知ったときにも、変化します。
他の人と音楽に対する話をして、同じ作品に対する評価を聞いてみること、或いは自分の知らない作品を教えてもらう事、そうする事で自分の音楽に対する価値観は常に流動的に変化していきます。
それは、他人の価値観を知る事により、自分の価値観の幅が広がると言う事です。
そうやって「楽しみ」を増やしていく事。
これも音楽に対するあり方の一つだと思います。
クラシックこそ本物で他は邪道、と言って憚らない人も、例えばロックなんかを聴いてみると、新しい世界が開けます。
もちろん聴いても変わらない人もいますが、それもそれで価値観です。否定はしません。
大事なのは他人の価値観を無下に否定しない事。これは音楽に限らず食い物の味でもそうですが。
否定をせず、聞く事。その上で自分が思ったことを確かめればいい。
議論自体は構わないけど、自分の価値観の決め付けや押し付けを前提としたものは、敢えてそれを楽しんでいる以外は、意味が薄いでしょうね。
その人がいいと思えるならば、クラシックでもロックでも演歌でもアニソンでもラップでも、何でも本物です。
音楽作品に貴賤無し。
総括。
音楽作品に対して、個人で評価出来るのは個人の価値観内にしかならない。
個人的な価値観の問題なので、自分が気に入った音楽作品について、周りの評価がどうあれ、自分の一番大事にすべきである。
もっとも他人の下す評価を聞く事も重要であり、それを持って更なる自己の価値観の向上につなげる姿勢も大事である。
価値観の問題なので、音楽作品に対する評価が分かれたとしても、それを無意味に否定する事は望ましくない。議論によって価値観の共有から止揚へとつなげる方が望ましい。
というところです。
この他にも、コマーシャルによる誘導とかコミュニティ内の価値観の方向性の整列力なんかも関係するのですが、ややこしいのでいずれ。
ただこの段階で少しだけ触れると、音楽作品に対する考え方と言うのは、音楽外の価値観によっても多大な影響を受けてしまう、と言う事が言えます。だからこそ総合的な価値観の問題になってくるのですが・・・
ご意見お待ちしております。
「ニ八そば やさと」 / 天もりそば ― 2007年04月10日 16時41分49秒
最近出来た蕎麦屋「やさと」さんに突撃。
場所は かわら亭さんの通り、都町側です。
駐車場は3台ほど。
お店は住宅兼店舗で、新築ピカピカです。

店内もまだ出来立てほやほや、というか新しすぎてスペースが使えてないというか、寂しい感じも。
席は4人掛けテーブルが4つ、カウンターが4席。計20席。
一先ず様子見と言う事で、「天もりそば」。天せいろです。

この時点でつゆを出し忘れてます。本当に出来たてのお店なんだなぁw
まずは蕎麦から。

つゆはちょうど中間ぐらいの味。濃さも普通です。ダシはやや物足りなさを感じます。全てにおいて中間の味です。
蕎麦は味、香りともに普通。ニ八だから香りや味はなかなか出ないでしょうね。コシは結構あり、噛んで食べる方がいいかな。
蕎麦とつゆの相性は悪く無いのですが、どちらも中庸な味わいなので、反面、個性を感じられません。
ビジョンが見えてこないですね、まだ。新しいお店なので、今後どうなるかは分かりませんが。
お次は天ぷら。

えび、なす、かぼちゃ、葉っぱ、まいたけ。
揚がりの色はとても上品です。
いざ食べてみると、揚げ過ぎ感はありませんが、逆にすっきりとは揚がっていないような。
予想ですが、油の温度を上げ切れていないのではないかと思います。
油の温度が低くなると、色目はきれいになりますが、反面衣が重くなるし、油の切れも悪くなる。確かに油が十分に切れず、紙に結構ついてしまっていました。
ここは改善の余地ありです。
まだ出来たてのお店と言う事で、味にしろ何にしろ不満点は出てもしょうがないですね。
張り紙にもご意見お待ちしています的な事が書いてありましたので、いろいろな人の意見を聞いて、さらに高みを目指してくださいな。
今の段階では、まだ評価は出来ません。しばらくは定点観測の必要あり、です。
場所は かわら亭さんの通り、都町側です。
駐車場は3台ほど。
お店は住宅兼店舗で、新築ピカピカです。
店内もまだ出来立てほやほや、というか新しすぎてスペースが使えてないというか、寂しい感じも。
席は4人掛けテーブルが4つ、カウンターが4席。計20席。
一先ず様子見と言う事で、「天もりそば」。天せいろです。
この時点でつゆを出し忘れてます。本当に出来たてのお店なんだなぁw
まずは蕎麦から。
つゆはちょうど中間ぐらいの味。濃さも普通です。ダシはやや物足りなさを感じます。全てにおいて中間の味です。
蕎麦は味、香りともに普通。ニ八だから香りや味はなかなか出ないでしょうね。コシは結構あり、噛んで食べる方がいいかな。
蕎麦とつゆの相性は悪く無いのですが、どちらも中庸な味わいなので、反面、個性を感じられません。
ビジョンが見えてこないですね、まだ。新しいお店なので、今後どうなるかは分かりませんが。
お次は天ぷら。
えび、なす、かぼちゃ、葉っぱ、まいたけ。
揚がりの色はとても上品です。
いざ食べてみると、揚げ過ぎ感はありませんが、逆にすっきりとは揚がっていないような。
予想ですが、油の温度を上げ切れていないのではないかと思います。
油の温度が低くなると、色目はきれいになりますが、反面衣が重くなるし、油の切れも悪くなる。確かに油が十分に切れず、紙に結構ついてしまっていました。
ここは改善の余地ありです。
まだ出来たてのお店と言う事で、味にしろ何にしろ不満点は出てもしょうがないですね。
張り紙にもご意見お待ちしています的な事が書いてありましたので、いろいろな人の意見を聞いて、さらに高みを目指してくださいな。
今の段階では、まだ評価は出来ません。しばらくは定点観測の必要あり、です。
茨城じゃなく千葉にある十二橋駅。間違えんなよ! ― 2007年04月12日 20時28分28秒
突然うなぎが食べたくなったので、佐原の「
うなぎ 山田」さんに行きました。
まあ前回と同じく並丼です。並でも十分量があるし、美味いですー。
例によって岩立の草もちも買いましたが、それだけだともったいないので、鹿島線の「十二橋駅(じゅうにきょうえき)」を見に行きました。
十二橋駅は鹿島線、香取駅の次の駅で、その次は茨城県にある潮来駅です。成田線と鹿島線が合わさっているので分かりにくいですが、鹿島線としては佐原駅が始点で香取駅で成田線と分岐します。
利根川を越えたところにあるので千葉と言う感じはしませんが、れっきとした千葉県香取市です。
十二橋、と言う名前から、 加藤洲十二橋 (引用元:香取市ウェブサイトさま)が真っ先に浮かびますが、十二橋駅から行くのは無謀です。たぶん駅に降り立った瞬間に途方に暮れます。
佐原駅からバスで水生植物園に向かうか、潮来駅まで行ってください。
香取駅から先の鹿島線は利根川を越えます。そのせいかずっと高架線になっています。
田園地帯なのに電車が高架なので、やけに目立つというかそれがかえって寂しさを煽るというか。
駅も当然ながら高架線上なので、高いところにあります。
ちなみに無人駅です。

駅前には砂利敷きの駐車場があります。トイレと公衆電話もあります。
ただし自動販売機はありませんでした。

白い建物は消防団の資材置き場かな。
まずは駅に向けて階段を上ります。

上がりきったところで下を見下ろすと。

ぽつぽつと民家などが見えますね。それ以外は田んぼです。
ホームに出て左手が潮来駅方面。右側が香取駅方面。


そしてホーム正面(東向き)。

ずーっと田んぼです。久々に地平線が見えそう・・・遠くには東関東自動車道が見えますね。
ちなみにこの地域一帯が田んぼなので、360°方向に田んぼが見えます。
それだけに、高いところにあるこの駅は、浮いてますねー。
待合室はちょっと新しい感じ。乗車駅証明書の発券機もあります。

最近千葉県の無人駅が次々と新築されているのですが、同じデザインですね。
ただしこの駅は高いところにあって周りに障害物が無く、相当風が強いかと思われます。
なので、待合室にはちゃんと壁があります。

ちと殺風景かな・・・
ダストボックスがありますが、自動販売機はありません。他の駅で買ったもの専用?
駅名表示板。ちょっとはげかけてます。

香取と潮来の間にあります。ちなみに香取駅も無人駅です。コンテナ車両をぶち抜いた造りだったけど、そろそろ新しくなっているかな・・・
駅を降りて駐車場に戻ると、黒い石碑が目に入りました。

なんか書いてありますね・・・という事で文字に起こしてみました。分かりにくい言葉には解説つきです。ヒマ人親切でしょ?でも間違ってたらごめんなさい。
つまりこの一帯の田んぼは、利根川の浚渫工事で出た浚渫土を使って整備されたと言う事ですか。
こんなに広大な土地にするのは並大抵の事ではないでしょう。頭が下がります。
こんなご苦労があってこそのお米です。大事に食べましょう。
興味本位で見に行った割には、歴史まで触れられて大満足です。
千葉というと南房総方面は割と明るいのですが、この北総も知ると面白いですね。
興味が尽きない県です。
まあ前回と同じく並丼です。並でも十分量があるし、美味いですー。
例によって岩立の草もちも買いましたが、それだけだともったいないので、鹿島線の「十二橋駅(じゅうにきょうえき)」を見に行きました。
十二橋駅は鹿島線、香取駅の次の駅で、その次は茨城県にある潮来駅です。成田線と鹿島線が合わさっているので分かりにくいですが、鹿島線としては佐原駅が始点で香取駅で成田線と分岐します。
利根川を越えたところにあるので千葉と言う感じはしませんが、れっきとした千葉県香取市です。
十二橋、と言う名前から、 加藤洲十二橋 (引用元:香取市ウェブサイトさま)が真っ先に浮かびますが、十二橋駅から行くのは無謀です。たぶん駅に降り立った瞬間に途方に暮れます。
佐原駅からバスで水生植物園に向かうか、潮来駅まで行ってください。
香取駅から先の鹿島線は利根川を越えます。そのせいかずっと高架線になっています。
田園地帯なのに電車が高架なので、やけに目立つというかそれがかえって寂しさを煽るというか。
駅も当然ながら高架線上なので、高いところにあります。
ちなみに無人駅です。

駅前には砂利敷きの駐車場があります。トイレと公衆電話もあります。
ただし自動販売機はありませんでした。

白い建物は消防団の資材置き場かな。
まずは駅に向けて階段を上ります。

上がりきったところで下を見下ろすと。

ぽつぽつと民家などが見えますね。それ以外は田んぼです。
ホームに出て左手が潮来駅方面。右側が香取駅方面。


そしてホーム正面(東向き)。

ずーっと田んぼです。久々に地平線が見えそう・・・遠くには東関東自動車道が見えますね。
ちなみにこの地域一帯が田んぼなので、360°方向に田んぼが見えます。
それだけに、高いところにあるこの駅は、浮いてますねー。
待合室はちょっと新しい感じ。乗車駅証明書の発券機もあります。

最近千葉県の無人駅が次々と新築されているのですが、同じデザインですね。
ただしこの駅は高いところにあって周りに障害物が無く、相当風が強いかと思われます。
なので、待合室にはちゃんと壁があります。

ちと殺風景かな・・・
ダストボックスがありますが、自動販売機はありません。他の駅で買ったもの専用?
駅名表示板。ちょっとはげかけてます。

香取と潮来の間にあります。ちなみに香取駅も無人駅です。コンテナ車両をぶち抜いた造りだったけど、そろそろ新しくなっているかな・・・
駅を降りて駐車場に戻ると、黒い石碑が目に入りました。

なんか書いてありますね・・・という事で文字に起こしてみました。分かりにくい言葉には解説つきです。
|
竣工記念之碑 理事長勲四等 新堀 正 書 香北土地改良区第三工区は日本水郷十 六島の北東部に位置し 早場米 はやばまい。 秋早くに出荷される新米。だいたい9月。 それよりも早い「超早場米」というのもあり、7月以降に出荷される。 の産地とし て知られた水稲単作地帯である。又舟を 使って耕地を往来して耕作に従事する詩 情豊かな農村として有名であった。 第二次世界大戦後の日本経済の急速な 成長に伴って農業機械の進歩大型化及び 運搬機材の自動車化等が進み、舟運によ る農耕では対応が不可能になり、農業基 盤の改良が必要となった。 たまたま建設省が利根川の改良工事を 計画し、この工事によって大量の 浚渫 しゅんせつ。 海底や河川などの水深を深くするために掘削すること。これによって航行可能船舶の幅を広げたり、容量のキャパシティを確保できる。 浚渫したときの土は廃棄物扱いのため容易に処分できない。有害物質の含有も問題視されている。 土 が生ずることを知り、この浚渫土を地域 内に 客土 きゃくど。 他の場所から性質の異なる土を持ってきて混ぜ合わせる事。これによって耕地の改良を行う。身近な例で言えば、ガーデニングの際に土に腐葉土を混ぜるなど。 して土地改良事業を施工するこ とについて受益者の要望が高まったので 県営 圃場 ほじょう。 田んぼ(田圃)や畑、菜園など農作物の発育場の意味。 整備事業を組合員全員の同意に 基づき申請し、昭和四十一年十月六日に 事業名千葉県営香北二ノ二地区圃場整備 事業として採択確定し、同四十二年四月 よりこの工事に着手した。 この事業の施工に当つて第三工区地域 内に既に小規模土地改良を施工した新島 第一土地改良区があつたが、諸施設を第 三工区に移管して再整備するためこの土 地改良区は解散した。 県圃事業費総額十九億七千九百萬円の うち国助成金九億四千九百萬円、県補助 金五億八千九百萬円、地元負担金四億四 千百萬円を投じ、有効幅員六米の農道、 幅員四米の排水路、パイプライン用水路 一筆五十アールの大型圃場等完成面積、 五百四十三ヘクタールを造成すると共に 十二橋駅を中心とする地域発展の素地を 整備したのである。 慈に組合員の努力と強力により理想の 農業基盤の完成を記念し、事業の経緯を 録し、先人の労苦に感謝すると同時に、 後人に吾筆の微意を伝えるものである。 昭和五十八年三月吉日 第三工区長 小倉康司撰文 歴代工区長 飯田二平 小倉兵二郎 |
つまりこの一帯の田んぼは、利根川の浚渫工事で出た浚渫土を使って整備されたと言う事ですか。
こんなに広大な土地にするのは並大抵の事ではないでしょう。頭が下がります。
こんなご苦労があってこそのお米です。大事に食べましょう。
興味本位で見に行った割には、歴史まで触れられて大満足です。
千葉というと南房総方面は割と明るいのですが、この北総も知ると面白いですね。
興味が尽きない県です。
「石臼自家製粉 手打ち蕎麦 三乗」 / 天せいろ ― 2007年04月18日 15時20分24秒
佐倉市は井野にあるお蕎麦屋さん「三乗」さんに行ってきました。
2006年の12月ごろに出来たという事で、まだ新しいぴかぴかのお店です。
場所は佐倉市井野。井野と言うと激しく渋滞する交差点として名高い場所ですね。テレビでも紹介されたぐらい。志津霊園のところでちょうど通りが分断されているので通り抜けできません。
最寄り駅は京成線の志津駅。歩いて10分ぐらいです。車だと駐車場が4台分ありますので、混んでいなければいけるでしょう。
お店はアパートの1階部分を店舗にした形式です。

店内も新しいです。ちょっと照明落とし気味の雰囲気で、大人の空間って感じですね。
席はテーブルが10人分、カウンターが5人分。こじんまりとしてます。
新規店舗のお約束、「天せいろ」を頂きました。

きれいにまとまっています。お箸にさりげなく店名のアピール。
最初はもちろん蕎麦からいきます。

つゆはやや濃いもので、醤油がかなり強い辛口です。ダシも強く、酸味があります。とはいえ切れ味の鋭い細身のつゆです。
蕎麦は味、香りともになかなかのもので、コシは普通です。ざらつきも程よく、噛んでも呑んでもいけます。
ややつゆが勝っている感じがしますね。つゆが江戸流儀の辛口なので、蕎麦もそれ相応に強くしないとバランスが取れないのが難しいところです。でもハイレベルなのは変わりません。
あと少し蕎麦の方が強くなれば、さらに素晴らしくなるでしょう。
今度は天ぷら。

小海老2尾、ふきのとう、まいたけ、れんこん、かぼちゃ。
お上品な揚げ方です。色は薄いですがしっかり揚がっています。衣が若干重たいかなぁ、とは思いますが、美味しく頂けますよ。
蕎麦も天ぷらも、上品な仕上がりです。美味しいですな。
佐倉のこの地域は渋滞が嫌なのでほとんど通らないのですが、いい蕎麦屋があるとなったらそういうわけにもいかないですね。
名刺をもらったので宣伝しときましょうか。
ちなみに終日禁煙です。ニコ厨煙草をお吸いの方は気をつけて下さい。
2007.05.20 追記

再訪。
鴨せいろを頂きました。実は人生初の鴨せいろです。
鴨の焦げ味がつゆに染みて、香ばしい風味となっています。鴨肉は2枚、あと肝がありました。
脂が乗っていて美味しい鴨ですね。
冷たい蕎麦と温かいつゆ、足すと答えは「ぬるい」。その点は少々不満ですが、味は美味しいものですね。
2009.06.18 追記
当時は鴨せいろの楽しみ方が分かってなかったなぁw
今ではすっかり鴨せいろの虜です。温度のコントラストがこうも味に影響するのかといういい勉強になりますよ。
2006年の12月ごろに出来たという事で、まだ新しいぴかぴかのお店です。
場所は佐倉市井野。井野と言うと激しく渋滞する交差点として名高い場所ですね。テレビでも紹介されたぐらい。志津霊園のところでちょうど通りが分断されているので通り抜けできません。
最寄り駅は京成線の志津駅。歩いて10分ぐらいです。車だと駐車場が4台分ありますので、混んでいなければいけるでしょう。
お店はアパートの1階部分を店舗にした形式です。
店内も新しいです。ちょっと照明落とし気味の雰囲気で、大人の空間って感じですね。
席はテーブルが10人分、カウンターが5人分。こじんまりとしてます。
新規店舗のお約束、「天せいろ」を頂きました。
きれいにまとまっています。お箸にさりげなく店名のアピール。
最初はもちろん蕎麦からいきます。
つゆはやや濃いもので、醤油がかなり強い辛口です。ダシも強く、酸味があります。とはいえ切れ味の鋭い細身のつゆです。
蕎麦は味、香りともになかなかのもので、コシは普通です。ざらつきも程よく、噛んでも呑んでもいけます。
ややつゆが勝っている感じがしますね。つゆが江戸流儀の辛口なので、蕎麦もそれ相応に強くしないとバランスが取れないのが難しいところです。でもハイレベルなのは変わりません。
あと少し蕎麦の方が強くなれば、さらに素晴らしくなるでしょう。
今度は天ぷら。
小海老2尾、ふきのとう、まいたけ、れんこん、かぼちゃ。
お上品な揚げ方です。色は薄いですがしっかり揚がっています。衣が若干重たいかなぁ、とは思いますが、美味しく頂けますよ。
蕎麦も天ぷらも、上品な仕上がりです。美味しいですな。
佐倉のこの地域は渋滞が嫌なのでほとんど通らないのですが、いい蕎麦屋があるとなったらそういうわけにもいかないですね。
名刺をもらったので宣伝しときましょうか。
石臼自家製粉
手打ち蕎麦 三乗
営業時間:
昼の部 11:30~15:00(ラストオーダー 14:30)
夜の部 17:30~21:00(ラストオーダー 20:30)
定休日 火曜日(祝祭日の場合は翌日休み)
駐車場 4台
〒285-0855 千葉県佐倉市井野1362-3
TEL&FAX 043-463-7880
ちなみに終日禁煙です。
2007.05.20 追記
再訪。
鴨せいろを頂きました。実は人生初の鴨せいろです。
鴨の焦げ味がつゆに染みて、香ばしい風味となっています。鴨肉は2枚、あと肝がありました。
脂が乗っていて美味しい鴨ですね。
冷たい蕎麦と温かいつゆ、足すと答えは「ぬるい」。その点は少々不満ですが、味は美味しいものですね。
2009.06.18 追記
当時は鴨せいろの楽しみ方が分かってなかったなぁw
今ではすっかり鴨せいろの虜です。温度のコントラストがこうも味に影響するのかといういい勉強になりますよ。

最近のコメント